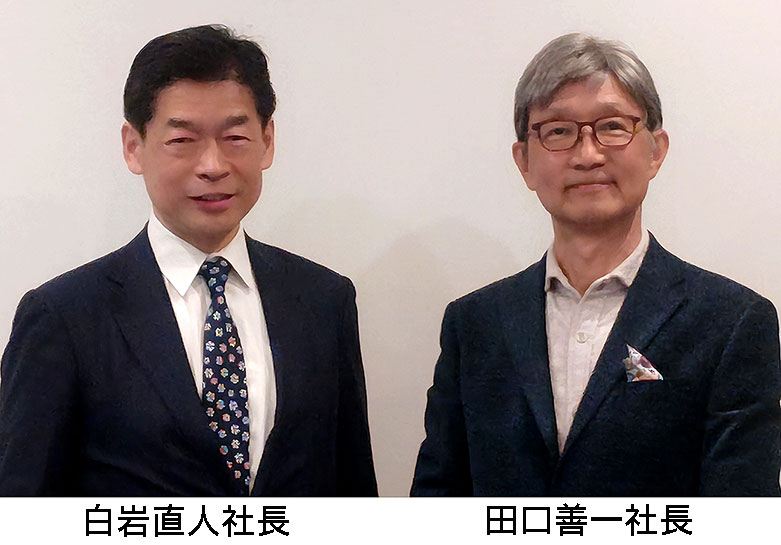JIA 白岩直人社長が聞く
「秘密分散」を他社製品に組み入れ
新進気鋭のIPO(新規上場)社長とジャパンインベストメントアドバイザー・白岩直人社長によるトップ対談。第三回目の対談相手は、3月27日に東証グロースに新規上場したZenmuTech(338A)の田口善一代表取締役社長CEO。同社は独自の秘密分散技術によって、PC内のデータを無意味化・分散することで情報を守る新発想のサイバーセキュリティを展開している。
白岩 まずは御社が将来目指す姿を聞かせてほしい。
田口 当社は単なる製品会社ではなくテクノロジー会社。われわれのエンジン(要素技術)をプログラムの一部として機器メーカーなどにOEM提供して、各メーカーの自社製品として世に出してもらおうというビジネス。要は素材、部品になるものを作っていこうと思っている。車、家電、PC、医療など日常のあらゆるシーンに組み込むことで、セキュリティを意識することなく、利便性も確保できる。将来的にロイヤリティ型のビジネスモデルを目指している。
白岩 テクノロジーの会社とあって、技術開発に膨大なコストがかかりそうだ。
田口 秘密分散と秘密計算のエンジンについては相当のノウハウが必要だが、当社の場合は産総研(産総研産業技術総合研究所)の技術的なバックアップで好循環ができているので、必要な部分に集中できる。
白岩 そもそも秘密分散とはどのような技術なのか。
田口 簡単に言えば、昔の割符(わりふ)を現代風にITで実現したもの。情報を暗号化した上で複数の分散片に分け、全てのかけらがそろわないと復元できない仕組みとなっている。そのため、仮に分散片が保管されているデバイスが盗難にあったとしても、シュレッダーにかけられたかけらを持っていたところで意味をなさない。今までデータは「守る」ものだったのに対し、われわれは真逆の「守らない」セキュリティだ。同時にそれをユーザーに意識させない利便性の高いセキュリティであり、価格も安い。
白岩 これだけ素晴らしいものであれば、もっと広まっても良さそうだ。
田口 (営業先では)新しいテクノロジーであるが故の抵抗感がある。旧型携帯電話からスマートフォンがスタンダートになるまで年数を要したように、これまでの常識を覆すモノの存在に人間はまず抵抗する。われわれもこれには大変苦労してきたが、ファーストペンギンの方々の導入を皮切りに、経営、IT部門、現場にとって三方良しのソリューションであるとの理解を得られるようになってきた。これをさらに広めるための上場だ。
白岩 秘密計算はどのような分野への応用が考えられるか。
田口 秘密分散によりデータを分割し、それを秘匿化したまま計算できることから様々なデータの利活用で期待されている。例えば、各銀行が持つ取引データを秘匿化したまま共有・分析して平均値や統計など得たい結果だけを抽出したり、不正検知の仕組みを構築して業界で共同利用したり。不動産分野では互いに情報を伏せたままマッチングさせて成約率を高めるなど、ほかにも様々な活用法が考えられる。ただし、秘密計算はこれからのテクノロジーなので、実用化には3~5年かかるとみている。
―――――――――――――――
田口善一氏プロフィール
SRA、日本オラクル、サン・ジャパンなどを経て、2002年より起業家に。14年3月にシンクライアント・ソリューション総合研究所(現ZenmuTech) 設立。
―――――――――――――――
白岩直人氏プロフィール
三和銀行(現、三菱UFJ銀行)を経て、45歳でジャパンインベストメントアドバイザーを創業し8年でマザーズ市場(当時)への上場を実現。金融商品の組成・販売などを中心に、主に金融ソリューション事業を展開し、日本全国に数千社の顧客基盤を有する。新規事業にも積極的に取り組み、2015年に日本証券新聞社を子会社化。
―――――――――――――――
≪取材後記≫
日本の情報セキュリティは世界から見ると大変立ち遅れています。
情報セキュリティに対する意識の低さ、危機意識の低さなどから対策が後回し、あるいは中途半端なものになりがちです。同社のような、有益で使いやすく、しかも安価なセキュリティシステムは既存の競合やベンダーからすると厄介な存在でしょうが、特に同社の主力システムであるZENMU Virtual Driveに関してはベンダーとも協業する営業戦略を立てているようですので同社の大いなる成長を感じることが出来ました。今後の飛躍に期待したいと思います。