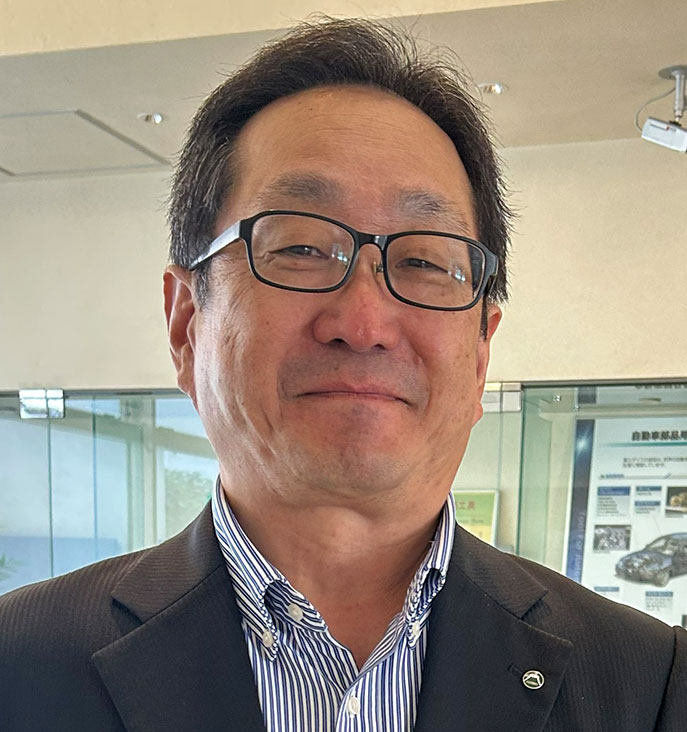今回は冨士ダイス(6167・P)の春田善和社長。「下町ロケットの印象の強い大田区下丸子の本社に伺ってお話を伺った。社名は「ダイス」となっているが、サイコロを作っているわけではない。「ダイス」は、電線やケーブル、精密なパイプや自動車用のパイプなどを作る際に使われる、引抜・押出加工用の工具だ。同社は、超硬合金製耐摩耗工具・金型の国内トップメーカーだ。社名の点のない「冨士」は成長に頂上はなく常に完成を目指して挑戦し続けるという願い表現だという。さりげなく強靭(きょうじん)な力を持った企業だ。
――業容を教えてください。
耐摩耗工具は、金属などに力を加えて所定の形に加工する時に使われる工具・金型のことです。金属などに大きな力を加えるので、摩耗に強いことが求められます。超硬合金はダイヤモンドに次いで硬いと言われています。
とても硬く摩耗に強い超硬合金を材料として工具や金型を作るためのコア技術が「粉末冶金技術」と「超精密加工技術」です。
「粉末冶金技術」とは、原料となる金属を混ぜ合わせた粉末を金型に入れて圧縮して形を作ったものを高温で焼いて、とても硬い超硬合金の素材を作る技術です。高温で焼くと20%くらい小さくなるので、それを計算して作るのに高い技術力が必要になります。
「超精密加工技術」は、1ミクロンのズレが許されない加工をする技術です。超硬合金はとても硬いので、ダイヤモンドの砥石(といし)で削るなど加工して磨いて工具や金型にするのですが、当社は高い加工技術を持っています。
――ものづくりを土台から支える「生命工具」とは?
当社の製品を「生命工具」と呼んでいます。ものづくりにおいては、材料や機械や人間がそろっていても、工具の精度次第でお客さまの製品そのものの命(品質)が決まってしまうためです。まさにお客さまの製品の生命を左右する責任を自覚し、常に世界最高水準の技術力でニーズにお応えしているため、当社製品は、ものづくりの様々な場面で使われています。
例えば、自動車の部品や半導体の生産、ビールやコーヒーの缶、エアコンなどの家電、カメラレンズなどを作る時にも当社の金型が使われています。キリがないくらい、たくさんのモノを作る時に使われています。皆さまが冨士ダイスの存在を意識されることはほとんどないと思いますが、実は生活のとても身近なシーンで皆さまのお役に立っている会社です。
――実際、多くの分野で御社の工具・金型・素材が貢献していますね。
当社は、76年の長きにわたって、その時々の成長分野の製品づくりに工具・金型を提供し、日本のものづくりを支えてきました。現在の成長分野と言われている次世代自動車の製造やAIデータセンターなどの次世代光通信でも、当社の工具・金型が使われています。特に次世代自動車では、センサー用レンズの金型、電源となる電池の金型、動力となる駆動モーターに欠かせないモーターコアの金型、半導体を作る装置の部品など、関連する製品が複数あります。
 櫻井英明(さくらい・えいめい)氏
櫻井英明(さくらい・えいめい)氏
最新経済動向を株式市場の観点から分析した独特の未来予測に定評がある。ラジオNIKKEIでは火曜「ザ・マネー 櫻井英明のかぶとびら」、木曜「櫻井英明のシン投資知識研究所」などに出演。
――今後の成長分野に向けた製品開発は?
コア技術の「精密加工技術」を活かして、AIデータセンターに使われる電子部品向けの金型の開発に取り組んでいます。具体的には次世代光通信に用いられる光ファイバーと光学部品を接続するコネクターの金型ですが、0.1ミクロンのズレも許されないレベルの加工精度が求められることが特徴です。レンズ金型の加工技術を応用することで求められる品質を段階的に達成しており、現状では国内でのトップランナーであると認識しています。
また、超硬耐摩耗工具づくりの技術力を活かして、新たな分野にも取り組んでいます。昨年、グリーン水素の製造装置向け電極を発表しました。コア技術の「粉末冶金技術」を応用して開発したもので、従来の水の電気分解に使用される電極に対し、消費電力を20%削減しました。現在テストが進行しており、2027年度の製品化を目指しています。超硬耐摩耗工具専業だった当社にとって、新たな分野への第一歩となる製品です。
――業績について。
中計期間最終年度の27年3月期の目標値は連結売上高200億円、営業利益20億円、経常利益率10.5%、ROE(自己資本利益率)7%を達成したいと考えています。