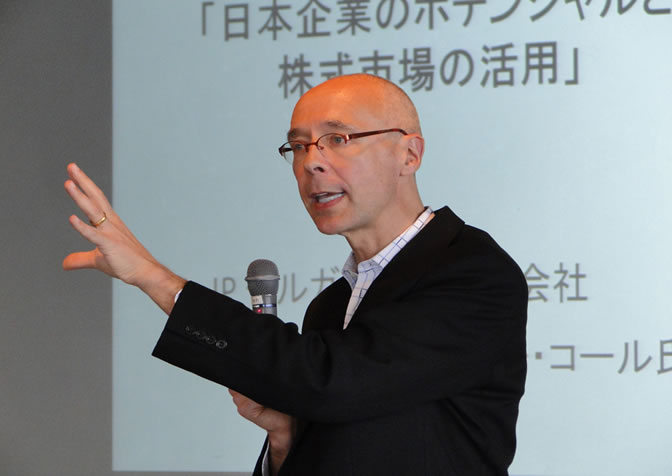 JPモルガン証券 調査部長
JPモルガン証券 調査部長イェスパー・コール氏
海外投資家の関心が日本に向き始めているという。そして2015年は「コーポレートガバナンス・コード」と「スチュワードシップ・コード」との両輪でもって、日本の上場企業が継続的成長に向けた取り組みを本格始動することも期待されている。そんな中、企業の戦略的なIR(投資家向け広報)の実践を支援する一般社団法人戦略的グローバルIR協会(SGIM)は2月24日、上場企業のIR担当者向けセミナーを開催。世界的エコノミストであり、日本企業を20年以上ウオッチし続けているイェスパー・コール氏を招き、海外投資家の日本株式市場への見方などが語られた。
海外投資家の「日本株イメージ」が改善
今年は年初より海外出張が続く。先ごろロンドンで行ったプレゼンテーションには30、40人が出席するなど、2、3人だった前年と比べて日本企業への関心の高まりを実感している。ヘッジファンドなど短期筋の関心はボラティリティの高い欧州へ向いており、生保など長期・安定投資家から説明を求められる機会が増えた。その理由をいくつか並べてみる。日本株への関心↑理由①割安感
数年前まで30倍台だった日本企業のPERが14-15倍程度と、英国やドイツなど他先進国並みの水準に落ち着いてきた。デフレが停滞する欧州に比べればファンダメンタルズも良好。海外投資家はあまたある世界各国市場をまずはPERなどでもってスクリーニングし投資対象を選定するため、割安感は被投資の重要な前提条件となる。日本株への関心↑理由②アナリストの世代交代
どちらかといえば“very bad job”だった海外金融機関の日本株アナリストに世代交代が起きている。バブル崩壊は遠い過去のはなし。彼らはフレッシュな目で日本企業を分析し、大手家電メーカーに対する凝り固まった先入観もない。日本企業の経営者にとって大きなチャンスが到来している。日本株への関心↑理由③経営者の意識改善
ジョージ・ソロスが日本に強気だったころ、彼は「日本で会社訪問をしてはいけない」と語っていた。職人文化が色濃く、経営者に「ROE(自己資本利益率)についてどう考えるか?」などと質問しても的確な回答が得られなかったため。そんな雰囲気もガラリと変わり、最近は大手企業のプレゼンテーション資料の冒頭にROE目標が掲げられるように。海外投資家がようやく経営者と対話できる土壌が日本企業でも育まれている。日本株への興味・理由④強力な政策フォロー
アベノミクスに対する詳細な評価はさて置き、消費増税の延期や法人税減税など、投資家の邪魔をする政策は今のところ見当たらない。金融緩和など“青信号”が多いこともポジティブ。安倍政権は昨年12月の総選挙で安定政権の基盤も手に入れた。一方、米国は金融業界などで規制強化の方向を向いており、投資環境的にはネガティブ。余談だが、料理がおいしくホテルのサービスも最高な日本への出張を望む外国人投資家の声も多数聞こえてくる。環境改善も円安がブレーキに…
しかしながら海外投資家の多くは日本株への投資判断をいまだオーバーウエートとはしていない。ドル建てで投資するため、円安を望む日本企業への投資は大きなリスクを伴う。昨年は日経平均が円ベースで7%上昇したが、急激な円安進展でドルベースは大幅下落となった。2015年日本株式市場の注目点
要注目は「銀行セクター」
今年は銀行セクターに注目している。長らく日本の低成長の要因だった設備投資の海外移転が、原油安などコスト低下で国内回帰することが期待されているため。加えて、今秋にもIPO(新規上場)を予定しているゆうちょ銀行に対する備えから、銀行セクターで配当水準向上の動きも期待される。ゆうちょ銀行は預貯金者の平均年齢が70歳を超えるなど成長性が大いに疑問視される。にもかかわらずIPOに踏み切るのには、東日本大震災の復興財源に充てるべく政府が保有株を売却するという特殊な事情が存在する。投資家に受け入れられるためにも4%程度の高配当が想定され、現在2.6-2.7%程度とするメガバンクもゆうちょへの乗り換えを防ぐべくこれに追随して株主還元策を拡充することが見込まれる。「株式持ち合い」の解消の進展もポジティブ。リスク資産を縮小させた銀行については増配の可能性がますます高まりそう。
次世代型IRがもたらすもの
例えば社外取締役。東証は先月、コーポレートガバナンス・コードの策定に伴い、社外取締役を2人以上専任することなどを盛り込んだ上場規則案を6月から実施すると発表した。しかしながら、私個人的には制度の強要や人数指定にはあまり意味がないと感じている。ただし制度そのものには肯定的で、数少ない優秀な経営陣を有効活用することは、日本の最大の課題「人材」の解決にもつながるだろう。社外取締役や女性登用など日本政府が掲げる政策のいくつかは西洋人の私からみればごく当然の習慣ではあるものの、一丸となって“まずはトライしよう”との姿勢も評価したい。トップダウンの政策のため、すんなり浸透する可能性もありそうだ。

[本紙3月20日付12面]
